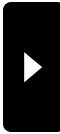2012年02月28日
やっと一週間!
(散歩道で見つけたモクレンの木の新芽たち)
白内障の手術からちょうど一週間が過ぎ、
やっと眼帯や保護用メガネから解放されました。
点眼液は3本あって、一日に4回目にささなければなりませんが、眼帯や保護用メガネの煩わしさからすれば、かなり楽です。
私は乱視があるので、視力は期待したほど伸びませんでした。
2012年02月25日
囲碁は私の宝物
私の趣味のひとつが、囲碁である。
学生時代に下宿にたまたま古い碁盤があり、たまたま下宿の学生仲間の
一人が碁のルールらしきものを知っていたので、並べてみた。
始めてみると、囲碁というゲームの深さにはまってしまった。
大学を卒業するころには初段格であったが、その後40年間、このゲームに
夢中になっている。
なんと奥の深い世界だろう! 若い世代の人たちが一人でも多くこの
囲碁に出会って、その魅力を知ってほしいと思う。
2012年02月24日
その3・・・テスト問題の落とし穴
今回は、学校における英語テストについて考えてみたい。 定期テストで英語担当教師が英語の問題を作り、先生が採点をする。ごく当たり前に思われるが、ここにも落とし穴がある。
<例> 次の英文の( )の語を正しく書き変えなさい。
① Tom ( study ) English every day.
正解は、( studies )であるが、もし( studys )と書いて生徒がいたら 教師はどうしますか。
おそらく私の経験ではほとんどの教師は、不正解として処理するであろう。
これは確かに、正答は一つであるが、( studys ) の答えに半分の点数を与えることは間違いであろうか?
studys も、studies も、音に出してみた場合には、まったく同じである。
この生徒は三単現のSを理解している。 ただ、study のような語は、y を i に変えてes を付ける、
ということをまだマスターしていなかったにすぎない。
このようなことが起こる原因は、その1でも触れたが、
英語教育が reading や文法問題に偏りすぎてきたことにある。
もし、speaking, listening にも等しく力点が置かれていたら、
studies とstudys は一方が正答で、もう一方はまったくの不正解だという結論にはならないと思う。
もうひとつは、教師がテスト問題を作るが、その問題そのものの質が問われなければならない。
一人の新米教師が作った未熟なテスト問題も、英語教育に精通した優秀な先生が作成した問題も
生徒にとっては同じである。
良いテスト問題とはどういうものなのか、校内で検討してほしいし、
採点に関しても、studys のような答えの扱いをどうしたらよいか、みなで検討してもらいたいのだ。
そうした地道な教師の努力が、「英語嫌い」を一人でもなくすことにつながっていくと信じている。
2012年02月22日
生まれて初めての手術
昨日、生まれて初めて「手術」を受けた。
いや、大したことはありません。「白内障」です。
手術の時間は、10分足らずでしたが、大変でした。
目の手術ですから、瞼を強制的に開けさせられ、
目の中にいろいろな色が飛び交い、
呼吸が生き苦しくなり、もう「やめてくれ!」と叫びたくなる心境でした。
今日、眼帯がとれて、目を保護する特殊メガネを着けるよう指示されました。
これは一週間着け続けなければなりません。至極不自由なり。
年をとるということは、こういう風に一つ一つの体の器官が、くたびれて、油が切れてくる
状態になるということ。気力だけは、とがんばっていくつもりです。
2012年02月20日
英語教育について その2
< 英語教育について > その2
今回は高校や大学入試に出される英語問題が、中学・高校の英語教育をゆがめていることを
指摘したい。
つまり、入試で英語特有なlistening, speaking、の力を測定する適切な方法がなかったために、
長い間、どうしても文法問題や長文読解などの問題に偏ってきたことは否めない。
その結果、中学、高校では、それに対応できる英語授業に偏ってしまった。授業では、文法や
読解に力点が置かれ、listening,speakingは二の次にされてきた。
それ結果、6年以上も英語を学習してきても、簡単な英語も聞き取れなかったり
話すことができない日本人が大勢生み出されてしまった。
解決方法などを述べるだけの力を私は持ち合わせていないが、
英語教育を大きく改善するには、英語を入試からはずし、資格試験とするような
思い切った手段もとる必要があるかもしれない。